ADFの見方: Bearing
もう少し実践的に。

いままでの図では、ADFのComapss Card (Azmuth)が固定式でした。
でも実際は、パイロットが自由に後ろのカードを回せるのが一般的です。
右の写真が多くの訓練機で見かける種類の一つです。
左下の「HDG」と書かれたノブを回すと後ろのコンパス・カードが回ります。
どんな使い方をするかは、自由ですが
通常ではHeadingとあわせる様にします。
すると、針が示すのが自動的にMBとなります。(RBでは先頭が000度を想定してます。)
注意はHeadingが変わると、意味が変わります。
水平飛行ではHeadingを不必要に変えないように。
また頻繁にHeadingが変わっていない事を確認してくださいね。
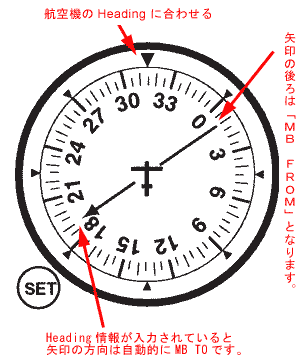
計器飛行での使い方になりますが、、、 (もちろんPrivateでも使えます)
コースに乗ると、Headingでは無く、
000度(360度か北)に合わせて使う場合もあります。
目的は横風対策に便利な方法なんです。
特にApproachではお勧めです。
使い方は人それぞれです。 一番見合った方法で使ってください。
教官から訓練を受けている方は、教官の指示で使って下さい。
色々な使い方が考えられるので、柔軟に対応して下さい。
左の図を見て頂ければ分かるのですが、ADFのカードを航空機のHeadingに合わせると、
自動的にMagnetic Bearingが分かります。矢印の方向が「TO」で、後ろがFROMとなります。
この場合は航空機がHeading 315 度を飛行していると想定しています。
針の方向が、局のある方向を示しています。
この場合でしたら、190度の方向に局があります。そして局が真後ろに来る方向、もしくは離れる方向が、矢印(針)の反対方向になります。 この場合でしたら、「010度、MB FROM」となります。
もちろんHeadingの情報が正しく無いと、意味がありませんので、この時は常時Heading Indicatorとの確認が必要です。中にはHeading Indicatorと同じになっている計器もあります。それはRMIと呼ばれます。種類によってはVOR局も選べます。